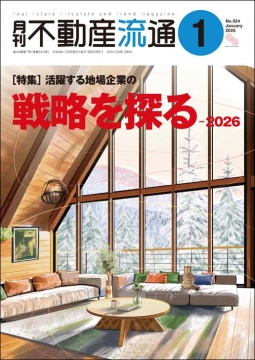東京・世田谷で小規模等価交換によるコーポラティブハウス誕生
小規模なマンションの購入希望者を集めて組合を結成し、計画段階から間取りなどを自由に設計できるコーポラティブハウス。そのコーディネイトを行なっているのが、(株)コプラス(東京都渋谷区、代表取締役:青木直之氏)だ。この度、同社2棟目となるコーポラティブハウス「Li Bell(リベル)」(東京都世田谷区、総戸数17戸)が竣工した。 先日行なわれた内覧会の様子をレポートしつつ、コーポラティブハウスの特徴について紹介していく。




ライフスタイルに対応した自由設計が魅力
「コーポラティブハウス」の魅力の一つとして挙げられるのは、何といっても自由設計。企画の段階から、建築家やコーディネーターと相談しながら、入居者自身が家づくりに携われるので、集合住宅でありながら、戸建注文住宅のように、間取りやデザイン、設備仕様、水回りの位置など、それぞれの生活スタイルに合った、こだわりの住まいをつくることができる。
コプラスは、建築家や住民の意見を調整しながら、建物のデザインや工事の発注などを決めていくコンサルティングを手掛けている。
「Li Bell」は、もともと借地権者が4名、底地権者が1名の土地。借地と底地を同時に整理して、小規模な等価交換を行なったプロジェクトだ。借地権者のうち2名と底地権者1名は、等価交換後の権利を売却して換金。「Li Bell」の全17戸中3戸は、残りの借地権者2名とその親族が所有者となり入居し、残り14戸を一般から募集した。
鉄筋コンクリート造地上6階建て、専有面積48.12~104.46平方メートル。世田谷線「若林」駅徒歩1分で、ターミナルの渋谷駅にも近い。都心部にありながら、周辺には大きな公園などがあり、利便性と住環境の両方を兼ね備えた立地だ。
建物の南側は緑道に面していて、日照も良好。すべての住戸が通風、採光、独立性が確保できる配棟となっている。
余分な経費をカットした合理的な住まい
見学した最上階6階にある夫婦世帯の住戸では、床は竹を使い、キッチンはオーダーメイド、玄関は風通しがいいように、引き出し式のオシャレな網戸を設置するなど、こだわりの内装となっていた。玄関に隣接する廊下の棚は、キッチンの棚と一体となっていて、両サイドから開くことができ、ゴミ出しなどがスムーズに行なえるようになっている。自宅兼事務所スペースとするため、部材や仕様にこだわり、オプションだけで1,000万円近く掛けているという。
そのほかの住戸も、標準仕様のままではなく、間取り変更をはじめ、壁に珪藻土を塗ったり、床材、水回り、照明や建具など一つひとつ好みのものに変更し、それぞれの入居者のこだわりが見られた。価格はファミリータイプのマンションと同じ程度の標準仕様の設備や内装仕上げ材を含んで3,370万~6,590万円。坪単価は、周辺相場が280万円のところ219万円と、大きく下回っている。東京・世田谷という都心エリアのわりには、リーズナブルな価格となっているため、ほとんどの住戸でオプションが加えられたという。
コーポラティブハウスは、大手ディベロッパーが、手を出さないような小規模の土地が対象なので、競合せず安く仕入れられ、その分、建物にお金を掛けられるメリットがある。また、住み手自ら事業に関わるので、土地取得費や建築工事費、設計費など、すべての事業費の内訳を把握できる。モデルルームなど広告宣伝費に多額の費用を掛けることもないので、通常の分譲マンションに比べて安く購入でき、合理的な住まいといえる。
“自分らしさ”と“コミュニティ”が購入の決め手に
購入者は30~40歳代のDINKSが大半で、その多くは、ライフスタイルに合わせて自由設計できることが決め手になった。また、良好な人間関係を築きやすいというのも大きな魅力だったという。入居前に数回集まり、管理規約など決めていく機会があるため、入居者同士自然と交流が始まり、入居前から全員が顔見知りになれる。
しかし、逆の見方をすれば、入居者同士のつながりが重視されるので、人と関わるのが苦手な人、干渉されたくない人にとっては不向きな住宅といえる。また、組合を組織してから完成まで、一般のマンション購入よりも多くの時間と手間が掛かる。こうしたことが面倒に感じる人にとっても向かない住宅だろう。さらに、希望者が集まらない場合や、途中で辞退する人がいた場合、計画が実現できないリスクも負うことになる。
同社取締役コーポラティブ事業部企画開発部執行役員の山口純一氏によると「コーポラティブハウスに入居する人の6割は普通のマンションを探していた人」と言う。「一般的には、まだあまり認知されていないので、はじめは躊躇される方もいますが、その仕組みや特長を理解されると、決断される方が多いですね」(同氏)と潜在的なニーズの高さがうかがえた。
多少の時間や手間が掛かっても、同じ価値観を持つ人が集まり、自分らしい暮らしが実現できるのなら、より住まいに愛着が持てていいのではないだろうか。
東日本大震災以降、人と人との絆が見直され、コミュニティのある暮らしに関心が高まっている。同じマンション内でも誰が暮らしているのか分からないのが当たり前の時代に、入居者同士のつながりを築けて、安心して暮らせるコーポラティブハウスは、貴重な存在といえる。
まだ市場規模の小さいコーポラティブハウスだが、今後供給戸数が増え、認知されるようになれば、一般的な住まいの選択肢に加わっていくのかもしれない。(さ)