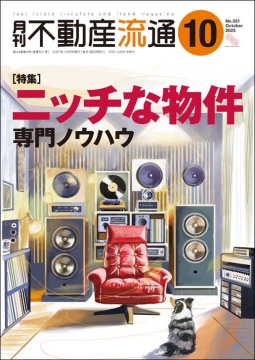独自の技術で資産価値を維持
福岡市中央区の建築設計事務所(株)福永博建築研究所(所長:福永 博氏)は、外配管システムを活用した長寿命マンションの普及をめざしている。同社が中心となって活動する会「300年住宅コンソーシアム」は、「平成21年度(第1回)長期優良住宅先導的モデル事業」に採択され、現在、4つのプロジェクトが進行中だ。このうちの一つで、同会会員の西日本鉄道(株)(福岡市中央区、取締役社長:竹島和幸氏)が事業主となった分譲マンション「ブライト・サンリヤン別府(べふ)シールズ」(福岡市城南区、総戸数41戸)が、2月に完成した。 本稿では、「長期優良住宅先導的モデル事業」として九州で初の竣工となった同物件の長寿命化へ向けた技術や取組みをご紹介したい。










「300年住宅」を提唱
福永博建築研究所は、建物単体ではなく、まちづくりと一体となった住宅供給でさまざまな実績を残している。同社では、社会の資産として長く住み継がれるマンションをつくることが、美しいまちづくりにもつながるという考えから、長期間にわたって住宅としての機能を保全できるマンション「300年住宅」を、20年も前から提唱、現在も普及に取り組んでいる。
「300年住宅」といっても、部材の老朽化が進むと住宅として機能せず、メンテナンスなしに長期間耐久することはできない。そこで同社では、資産価値を維持しやすいように、独自に開発した技術や、運用の仕組みを提案している。
「現在のマンションは、建物が古くなっても、住民の合意が得られず、大規模修繕などを行なうことができないケースが多い。そのまま放置すれば、住宅としての機能を失って、資産価値がなくなってしまう」と、同社所長の福永 博氏は、日本の住宅の将来を危惧している。
同氏が「300年住宅」を提唱した当初は、まだ世論が形成されておらず、理解されにくかったというが、現在では、政策も「ストック型」へと転換し、長期に循環利用できる質の高い住宅づくりが注目されるようになった。
自ら事業主となり、「300年住宅」を分譲してきた同社では、さまざまな技術を独自に開発。これまで100項目を超す特許を取得している。ディベロッパーやゼネコンに、同社が培った技術を有料で提供し、長寿命マンションの普及をめざしたが、なかなか事業化には至らなかった。
そこで同社は、300年住宅型マンションを供給・販売してくれる事業パートナーを探すべく、2009年12月に「300年住宅コンソーシアム」を立ち上げた。会員には「300年住宅」に関する、登録済みの商標や、同社が取得している特許を、すべて無料で提供している。
現在は、西日本鉄道、伊藤忠都市開発(株)をはじめ、電力会社やガス会社なども会員となっており、同社は技術開発に特化して、事業をサポートしている。
長寿命を可能にする「外配管システム」
今回紹介する分譲マンション「ブライト・サンリヤン別府シールズ」は、地下鉄七隈線「別府」駅から徒歩7分の立地。
鉄筋コンクリート造地上7階建て、敷地面積2,518.65平方メートル、延床面積4,063.87平方メートル。専有面積は78.11~105.04平方メートル(間取りは3LDK・4LDK)、竣工は1月19日、入居開始は2011年3月下旬。
同マンションは、共用の排水管を、廊下とベランダに設けた「外配管システム」にすることによって、長寿命を実現している。
一般的には、専用部の中をタテに貫く内配管が主流だが、これだと修繕時に専有部の壁や床を壊す必要があり、住民の合意が取りにくいことから、改修が進まないケースが多い。30年以上使用すると、いくら躯体の耐用年数が長くても、配管は寿命となり、住み続けることができなくなってしまう。外配管であれば、メンテナンスや交換が簡単にできるため、建物を長く使うことが可能になるというわけだ。
また、同社では、設備のメンテナンスや交換をスムーズに行なえる「シャフトボックス」を独自に開発。300mm×500mmのコンパクトなスペースに、排水管をはじめ、水道管、ガス管、電線などをまとめて収納したもので、交換時の手順を考慮して、精密にプレートの位置を設計している。「シャフトボックス」内には、あらかじめ予備の配管スペースを設けているため、古い配管を付けたまま新しい配管を設置でき、住民が生活しながらでも工事を行なえるという。また、外の枠組みを簡単に取り外すことができ、設備交換の際には、解体・移動して工事スペースの確保もできる。システムを部品化して、コストの削減を図るなど、ディベロッパーが採用しやすいよう事業性にも配慮しているのだ。
これまで外配管が普及してこなかった原因の一つに、階高の問題が挙げられる。
外配管にすると、専有部の床下配管に傾斜を付けなければならず、より深い床下空間が必要になるため、これまで高さ規制のあるエリアでは事業上のネックになっていた。しかし同社では、外配管を、各住戸の入り口脇にある「シャフトボックス」内と、ベランダの2ヵ所に設置。2方向に分散させることで、床下配管の傾斜を緩め、その分高さの制限を緩和させることに成功。
建設コストも1戸当たり12万円程度の増額で抑えられるため、ディベロッパーも採算が取りやすく、導入に踏み切りやすい。
一方、通常、専用部の中をタテに貫く内配管は、トイレやキッチンの横にあるため、水回りの位置は変更できないケースが多い。しかし、同物件は、各専有部の床下に、外配管とつながる横引き管を設け、「主管」と「枝管」に機能分けすることで、水回りの位置を自由に動かすことを可能にした。しかも、主管の真上の床は開閉できる仕組みで、簡単にメンテナンスや交換をすることができる。
加えて、同物件では、地下ピットを設けて集合横引き管を配置。共用配管を土やコンクリートで埋めずに、人が入ってメンテナンスできる構造にしている。
通常は、壊れた箇所が出てきたら、覆っている土やコンクリートなど、すべてを掘り起こさなければならなかったが、事前に点検・メンテナンスができ、万が一壊れてもすぐにその部分だけ交換すればいいので、将来の工費を抑えられる。
こうした工夫を積み重ねることにより、住み始めてからのランニングコストに大きな差が生れてくるという。
同社では、今後も、これから開発されるマンションや、既存マンションの大規模改修時に、現在の内配管ではなく外配管にして、30年~50年ごとに共用設備の配管類をすべて更新することを提案していく。
低コスト・低メンテナンスを実現する、さまざまな工夫
そのほか、間取りの自由性も実現するため、同社では、「トリプル壁」を開発。これは、開口部の全面を一体のサッシュとしたもので、サッシュ枠に組み込まれたレール上にボードを取り付け、室外部に給湯器、エアコンの室外機などを設置し、小壁の代わりとしている。
ボードはビスで留めているだけなので、簡単に動かすことが可能。これまでは動かなかったバルコニー側の窓や小壁の位置を簡単に移動することができ、これによって間取りの自由度がさらに増した。
また、同物件では、バルコニーや共用廊下の腰壁にレンガを採用。穴あきのレンガを使って、中に鉄筋を入れることで補強している。自然素材なので、吹き付け塗装やタイルの場合と比べて、はげ落ちる心配がなく、逆に経年変化が味になっていくという。
レンガは、建物の表面積の約20%を占めており、この部分がメンテナンスフリーとなるため、大規模修繕の際にコストを減らす有効な手段になるようだ。
さらに、熱帯材を利用したコンパネを使わないため、建設時の省CO2にも貢献している。
一方、屋上も防水を二重にすることで、修繕の期間を50年に延ばしている。二重の防水層の間には、通水と通気のための溝を設置。万が一、上層の痛んだ部分から漏水があったとしても、下層で水を止めて排水する。
通常のマンションでは、25年程度で全面張替えを行なうというが、二重防水であれば、下層は紫外線や雨風にさらされることがないので、劣化を免れ、メンテナンス頻度を減らすことができる。
そのほかにも、外壁の要所にボルトを設置して、ちょっとした補修は足場を組まずに行なえるように工夫していた。足場を架けるような大規模な改修工事は、共用配管の取替えと同じタイミングでまとめて行ない、無駄な工費を抑えていくという。
また、コンクリートの間には金物の打継ぎを入れて水切りを良くし、将来の外壁の汚れを少なくするなど、美観を守る工夫も取り入れている。
さらに、住棟には、植栽を配したオープンスペースを設置。時間の経過と共に緑が育ち、建物と調和するように意識したという。
50年先、100年先も長く住める建物にするには、こうした工夫で工費を抑えたり、資産価値を保つ仕組みづくりが大事なのだと改めて感じた。
自由に変更できる!水回り・間取りが人気に
同物件の販売価格は3,000万~4,450万円。周辺相場よりもやや割高な設定ながら、順調な売れ行きとなり、30~60歳代と幅広い年齢層を集め、竣工時にはほぼ完売の状態となった。
購入者は自営業、公務員など、年収が高めの人が多く、一次取得よりも、住替えのニーズが強い傾向で、住まいにこだわりを持つ人が多く集まったという。
顧客には、ライフスタイルの変化に合わせて、水回りや間取りを自由に動かせることが好評で、自由設計を生かして、41戸のうち30戸に設計変更が入った。
「マンションを資産として、長期間にわたって価値を保全したいと考える消費者はたくさんいらっしゃいます。これからも多くの事業者に、長寿命マンションを普及させていきたい」と福永氏は話す。
来年1月には、山口や博多などで進行している、他3つの長寿命マンションも完成する予定。日本の住宅の価値を保全していく同社の取組みを、今後も注目していきたい。(さ)