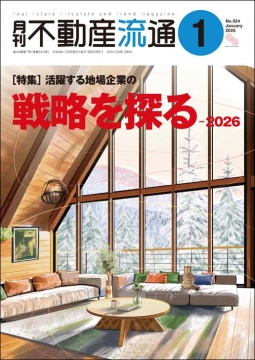世界遺産カッパドキア
日本の約2倍の広さがあるトルコは、国土の大部分が高原となり、その中心部アナトリア高原にあるのがカッパドキアです。

カッパドキアには、現在は死火山となっている3つの山(エルジエス山、ハサン山、ギュルル山)があり、これらが活火山であった約7,000万年前以降に始まったとされる火山活動により、大量の溶岩や灰が噴出し、それらが堆積して100~200mほどになる凝灰岩の地層が作られました。
これらの地層は何万年もの年月をかけて、風雨の浸食によりけずり取られていき、それによりラクダやキノコのような奇妙な岩が広がる世界に類を見ない不思議な景観が生まれたのです。
このような奇岩(火山岩)を掘って作られたのが洞窟の家であり、紀元前3,000年頃から人びとはこの洞窟の家で暮らすようになりました。
カッパドキアの洞窟の歴史

カッパドキア地方に人が住み始めたのは、先史時代に遡ります。カッパドキアは初期青銅器時代の幅広い交易によりアッシリア文明の影響を受け、この文明時代に文字が導入されました。
また、カッパドキアは、その立地条件から重要な意味を持つ戦略上の拠点とされてきました。
カッパドキア地方はしばしば、その市場や資源を狙った侵略、侵入、略奪の対象となっていきます。こうした略奪者たちから身を守るため、地元の住民たちは敵から気づかれないよう入り口を隠すことができる大小の洞窟に住むようになりました。このようなシェルターの役目をした洞窟は現在カッパドキアに250ほど見つかっています。
研究者は、ヒッタイトとその末裔の時代に多くの洞窟が地下に作られたと考えており、身をひそめる生活が長引くことも予想されたため、この穴居住居は最終的に水源、食物貯蔵庫、ワイナリー、寺院などを含む地下都市へと発展していきました。
洞窟の家の利便性

15世紀までにオスマン帝国がカッパドキアを領有するようになると、この地に住もうと移住してきたオスマントルコ人たちは、新しく自分達の洞窟の家を作って住み始めます。
カッパドキアの火山岩は、極小の孔による多孔質であるため、優れた断熱性があり、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができることに気がついたのです。
洞窟の家には、決められた目的のために使われる部屋を決めています。例えば、日当たりのない暗く涼しい場所は、じゃがいも、干しブドウなどの貯蔵庫として使われます。洞窟の中は保湿性に優れているため、冷蔵庫のように食材を何ヵ月も保存できるのです。そして暖かく明るい部屋は台所やリビングルームとして使われます。
現在は利用されることがありませんが、洞窟の家の一番上は、鳩小屋の空間としていました。カッパドキアの農地では、古くから鳩小屋の鳩糞が畑の有機肥料として使われていました。現在は衛生上やコストの問題で、既製の有機肥料が使われており、鳩小屋の役目はありません。
洞窟の家をホテルへ改装
世界に類を見ない奇岩の風景と洞窟住居で、カッパドキアは1985年にユネスコの世界文化遺産に登録されました。その後、洞窟の家の価値が急上昇したことから、現在は洞窟の家をホテルに改修しているところがほとんどです。

|

|
洞窟ホテルは、部屋数が少ないこともあり、一般のホテルより割高ですが、観光客に大人気でシーズン中は予約が取ることが難しくなります。
このような洞窟ホテルブームにより、洞窟の家が投資物件となり、またトルコの近年のインフレも伴い、現在は日本円にして数千万円以上の価値がついています。そのため、行政が文化保存のために補助をして存続させている洞窟の家も存在しています。

横溝絢子
銀行員として5年以上住んだニューヨークを離れ、トルコの田舎町、カッパドキアの大ファンになり、移住。連載執筆、メディア出演実績などは以下。地球の歩き方イスタンブール特派員(連載中)、NHK BS1「世界で花咲け! なでしこたち」、メディアファクトリー「ヤマザキマリのアジアで花咲け! なでしこたち」、BSジャパン「速水もこみち トルコ食紀行」、読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」、毎日放送「世界の日本人妻は見た! 」、NHKラジオ第1「ちきゅうラジオ」、TOKYO FM「コスモ アースコンシャス アクト」など。海外書き人クラブ所属。