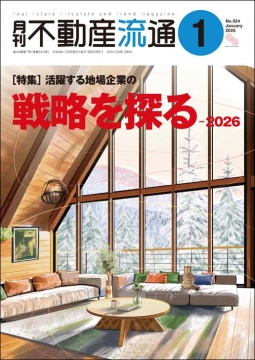(社)全国宅地建物取引業協会連合会会長・(社)全国宅地建物取引業保証協会会長・伊藤 博氏
(社)不動産協会理事長・岩沙弘道氏
(社)不動産流通経営協会理事長・大橋正義氏
(社)不動産証券化協会理事長・岩沙弘道氏
(社)日本ビルヂング協会連合会・髙木丈太郎氏
(社)住宅生産団体連合会会長・樋口武男氏
(財)日本賃貸住宅管理協会会長・三好 修氏
一般社団法人日本増改築産業協会会長・中林幸一氏
(社)日本インテリアファブリックス協会会長・吉川一三氏
(順不同)
■(社)全国宅地建物取引業協会連合会会長・(社)全国宅地建物取引業保証協会会長・伊藤 博氏
「業界のオピニオンリーダーの役割を果たし、国民の住生活の安定向上を目指す」
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は、みなさま方のご支援とご協力により、円滑な組織運営ができましたことに感謝申し上げます。
昨年の我が国の経済は、国民の景気実感を反映している名目GDPの成長率がマイナスとなり、失業率も高水準で推移するなど、厳しい状況でありました。
不動産市場では、平成21年の年間住宅着工件数は80万戸を切ることが予想されるなど激減し、地価公示と都道府県地価調査の結果は、全国的な地価下落の傾向を示すものとなりました。
また、昨年の衆議院議員選挙で政権が交代し、土地住宅税制・政策等を提言する環境が大きく変わりました。
こうした中、全宅連では、住宅市場の活性化は、国民の生活基盤の確立のみならず、我が国経済のけん引役を果たしており、住宅不動産政策の推進が重要であるとの認識から、都道府県宅建協会と連携し、政府に対して、平成22年度税制改正・土地住宅政策について提言をしてまいりました。
この結果、政府税制改正大綱において、適用期限を迎える各種税制の特例措置の延長と住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡大という成果を得ることができましたことは、みなさま方のご協力によるものであり、深く感謝申し上げる次第であります。
本年の活動について申しますと、組織運営面では、昨年6月の通常総会において、全宅保証とともに、公益法人改革関連3法に対応し、公益社団法人への移行認定を目指す決議をしたことを踏まえて、組織、財務体制を含めた準備を進めてまいります。
業務支援事業の実施としては、月間アクセス400万件、物件数30万件を誇る「ハトマークサイト」において、パソコン操作に不慣れな方のためのファックスによる代行登録と、必須項目のみを物件登録する「かんたん登録」画面の構築などにより更なる利用促進を図るとともに、賃貸不動産管理において、賃貸不動産管理業の独立性・健全性、社会的信用の確保を目的として「賃貸不動産経営管理士」制度を推進し、賃貸不動産管理業の法制化に向けた活動を展開してまいります。
事業環境の整備・改善活動としては、不動産流通市場の活性化のために、既存住宅の流通促進に関する各種施策について提言を行うとともに、取引制度研究会において早期・安全・確実な不動産取引が行える「不動産取引所」の検討を続けてまいります。全宅連不動産総合研究所においては、不動産業を取り巻く法制度や経済・社会情勢の変動に対応した土地住宅税制・政策等に関する提言の研究を実施してまいります。また、不動産取引全般を網羅する「不動産取引法」の研究も行ってまいります。
全宅連では、本年も不動産業界最大の団体として業界のオピニオンリーダーの役割を果たしていくとともに、消費者利益の擁護、増進に努め、国民の住生活の安定向上を目指す等、公益活動も推進してまいります。
最後に会員のみなさま方のますますのご繁栄とご健勝をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
世界経済は、各国の政策効果により最悪期は脱しつつあるものの、予断を許さない状況が続いている。雇用や所得を巡る環境悪化から、個人消費を始めとする需要の低迷が継続しており、本格的な景気回復には相当の時間を要するものと考えている。
一方、わが国経済についても、アジアを中心に外需に持ち直しの動きが見えるが、雇用や消費に改善の兆しが見られず、また、政府の月例経済報告では、「緩やかなデフレ状況にある」との認識が示され、加えて円高の影響も懸念されるなど、依然楽観を許さない状況が続いている。
政府におかれては、景気の底割れを防ぐよう、2次補正予算の早期実施を急ぐとともに、内需主導による成長戦略の具体的な道筋を示し、「景気の二番底」を回避すべく危機感を持って迅速に対応して頂くことを切に願っている。
昨年は、我が国の不動産市場にとって、極めて厳しい一年であった。
賃貸オフィス市場は、企業業績の悪化の影響を受け、空室率の上昇が続いた。本年についても、実体経済の回復が依然として不透明であるが、景気動向、市場動向を引き続き注意深く見つつ、新規需要の喚起や、業務集積度の向上に対応するなど、テナントニーズを的確に捉え、きめ細やかな顧客対応が必要であると考えている。
また、新築住宅着工戸数は、42年ぶりに年間100万戸を切り、70万戸台に大幅に落ち込む一方で、首都圏のマンション市場は、販売在庫が7千戸を切る水準まで着実に減少し、平均契約率は5月以降概ね70%で推移するなど、売れ行きは回復傾向にある。
不動産投資市場については、いわゆるリーマンショック後、世界的な信用収縮の影響を受け、資金調達環境は厳しい状況が続いていた。その後、金融市場が正常化に向かう中、昨秋以降、不動産市場安定化ファンドの創設やJリートの再編の動きから金融機関や投資家の不安が軽減され、Jリートによる公募増資や新たな私募ファンドの組成が発表されるなど、徐々に資金流入が改善されつつある。昨年は、都心の大型ビルにおいて、市場予測を上回る高値で売買取引が成立するなど、東京のオフィスマーケットの強さが証明された。
こうした中、昨年9月の政権交代により発足した民主党政権において、12月8日、「明日(あした)の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定された。住宅投資の拡大のため、「フラット35S」の金利の大幅な時限的引き下げ等の住宅金融の拡充措置や、住宅版エコポイント制度の創設、建築確認手続き等の運用改善等の施策が打ち出された。
また、22日にまとめられた「政府税制改正大綱」では、当協会が強く要望した「住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大」が実現し、「居住用財産の買換え特例」や「新築住宅の固定資産税軽減特例」をはじめとする住宅・不動産税制の特例措置の延長が認められた。
中でも、「住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大」は、平成22年中に贈与を受ける場合の非課税限度額は1,500万円、平成23年中は1,000万円と非課税枠が大幅に拡充された。シニア世代が保有する金融資産を活用して、若年層の住宅取得を促進させる大変有意義な措置であると高く評価出来る。当協会会員企業も、この措置を活かし、住宅販売の促進に一層努めるとともに、新築住宅着工戸数を回復させなければならない。
さらに、国土交通省の成長戦略会議においても「住宅・都市」分野が柱のひとつとして位置づけられ、住宅市場の活性化や都市再生に向けた検討が進められている。
このように、政府においても資産デフレの回避や、内需拡大のために、住宅・不動産市場の活性化が不可欠であるとの認識のもと、政策に取り組んでいただいている。
景気は、本年も引き続き予断を許さない状況にあり、今後も官民が一体となって市場回復に向けた取り組みを進めなければならない。
会員各社は、政府から示された対策を活かしつつ、お客様に満足いただける安全、安心で環境に優しい住宅の供給や、都市・地域再生に取り組むことにより、国民生活の向上と日本経済の発展に貢献してまいりたい。
「流通新時代」に向けて、消費者の視点を踏まえた、積極的な取り組みを
年頭にあたって謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
皆様には、佳き年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年の不動産流通業界においては、既存住宅流通市場が、大幅な価格調整に加え、住宅ローン減税の拡充などの対策により取引件数が増加に転じ、住宅取得需要が回復に向かう兆しが見られるものの、新築住宅市場は、事業者向け貸し出しが厳しい状況から在庫調整に努めるなど、新規住宅着工戸数の減少傾向が顕著となっており、不動産投資市場の低迷と相まって、依然厳しい状況になってきております。
このような経済環境のもと、昨年末発表された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において、優良住宅取得支援制度(フラット35S)の金利の大幅な引き下げ、住宅投資の促進に資する贈与税の措置の拡大等の税制改正、更には住宅版エコポイント制度の創設等により住宅投資・設備投資への支援による景気対策を目指す方向が示されました。これらは、低迷する新築住宅市場を下支えし住宅流通市場に好影響を与えるものと期待されます。
不動産流通市場の円滑化、活性化に向けた政策面では、民主党による新たな政権下において、長期優良住宅の普及促進をはじめ、省エネ化、バリアフリー化、耐震化を目的とした既存住宅の活用や安心な取引で中古市場を活性化することなどが示されており、長期にわたり住宅が維持され、流通するに際しての具体的な方策の検討が進められております。
このような状況の中、当協会では、「流通促進施策検討研究会」を昨年より立ち上げ、流通市場の活性化に向けた業界としての取組を検討してきました。既存住宅の取引に際し、耐震診断やホームインスぺクション、リフォームプランをパッケージ化にして提案することにより、売主、買主の不安や不満を解消し、既存住宅への需要を高めていくことを具体的に取りまとめてまいりたいと考えております。
また、本年は、当協会設立40周年という節目の年を迎えます。既存住宅市場が新築市場に匹敵する「流通新時代」に向け、仲介サービスの向上と市場の透明性を高めるため、消費者の視点を踏まえた政策提言など活発な事業展開を行ってまいりたいと存じます。
我が国経済は、企業業績や雇用情勢など予断を許さない状況にあります。
このような経済情勢の変化に注視しつつ、明るさの見え始めた不動産流通市場を確かな成長軌道に乗せるため、皆様方のご理解、ご協力のほど、引き続きよろしくお願いいたします。
「不動産投資市場の活性化で内需主導の景気回復を」
皆様、新年あけましておめでとうございます。
世界経済は、各国の政策効果により最悪期は脱しつつあるものの、予断を許さない状況が続いております。雇用や所得を巡る環境悪化から、個人消費を始めとする需要の低迷が継続しており、本格的な景気回復には相当の時間を要するものと考えます。
一方、わが国経済についても、アジアを中心に外需に持ち直しの動きが見えますが、雇用や消費に改善の兆しが見られず、依然楽観を許さない状況が続いています。12月の月例経済報告でも、物価動向については、11月報告に引続き「緩やかなデフレ状況にある」と指摘されており、景気の底割れが懸念されます。
新政権には、2次補正予算の早期実施を急ぐとともに、内需主導による成長戦略の道筋を示し、デフレの進行を防ぐよう危機感を持って対応して頂くことを大切に願います。また、日銀には、政府施策と歩調を合わせ、デフレ克服のために迅速果敢な金融政策の実施を期待いたします。
わが国不動産投資市場は、一昨年のリーマンショック以降、世界的な金融市場の混乱および急速な信用収縮によって大きな打撃を受けましたが、その後は政府の経済危機対策にもとづく「不動産市場安定化ファンド」の創設などの動きから、金融機関や投資家の不安が軽減され、昨秋以降はJリートによる公募増資や新たな私慕ファンドの組成が発表されるなど、徐々に資金流入が進み、回復の兆しが見られます。また、苦境にあったいくつかの投資法人についても、新スポンサーの選定や合併による再編が進んでおり、今後の市場の発展につながる対応が図られ、新たな成長に向けて第一歩を踏み出したといえます。
Jリートをはじめとする不動産証券化商品は、ミドルリスク・ミドルリターンの投資商品を投資家に提供するとともに、国民生活の基盤である都市や地域の再生による優良なストックの形成を通じて、雇用の拡大や、国民生活の向上に大きく寄与するものです。また、経済のグローバル化・ボーダーレス化に伴い、世界規模で運用される資金が成長市場に収斂する動きが加速する中、こうした資金を呼び込むためにも、都市や地域を再生・活性化し、その魅力を高めていくことは、わが国の国際競争力の向上にとっても喫緊の課題であり、官・民が協調して邁進すべきものだと考えます。
こうした中、平成22年度税制改正大綱において、当協会がかねてより要望していた「投資法人等の登録免許税の軽減措置の延長」、「特定社債の募集要件の緩和」、「海外投資家が受け取る投資法人債等の利子に係る非課税措置の創設」が措置されたことは、市場の活性化ならびに資産デフレの防止にとって非常に有効であるとともに、Jリートなど不動産証券化商品の役割を十分に評価いただいた結果として、たいへん高く評価することができます。
このような厳しい経済情勢の時にこそ、さらなる市場の発展を見据えた諸活動に取り組んでいかねばなりません。当協会では、第三期中期目標として「不動産投資市場の再生と信認回復」を掲げていますが、本年はその達成に向けて「商品性の向上」と「投資家層の拡大」に取り組みたく思います。
「商品性の向上」に向けては、合併、再編や外部成長を支援する税制改正・制度改善・資金調達環境の改善に向けた活動に注力し、投資対象としてのJリートの魅力度アップを図る運用会社やスポンサーを支援して参ります。
また、「投資家層の拡大」に向けては、年金フォーラムや個人投資家のためのJリートフェアを始めとする広報・啓蒙活動に一層力を入れ、不動産証券化商品の特性や魅力についてより多くの年金基金、個人投資家に御理解を頂くよう尽力して参ります。
新年おめでとうございます。
2009年は日本の政治・経済にとって歴史に残る1年となりそうです。
総選挙での国民の選択によって、本格的な政権交代が行われました。
新政権の下で、これまでの行財政システムについて抜本的な見直しが進められており、効率的な行政を求める立場から共感を覚える部分も少なくありません。ただ、残念ながら長期の国家ビジョンとりわけ経済成長戦略がまだ見えてきておりません。わが国の政治・経済を確かな方向に牽引していただけることを願っております。
わが国の経済は、‘07年に顕在化した米国のサブプライムローン問題と、それに続く’08年9月のリーマンショックを契機に、大きな荒波に曝されました。その深刻な影響は、オフィスビル市場を含む不動産事業全般にわたり、各企業において経営環境の悪化が懸念される状態にあります。
そうした中、鳩山総理は9月22日、主要輩出国の参加を前提に2020年までに「1990年比25%削減」という温室効果ガス削減の中期目標を表明されました。
私どもも、温室効果ガスの削減は、地球の未来のために強力に推進すべき喫緊のテーマと考えており、一昨年、「ビルエネルギー運用管理ガイドライン」をとりまとめ、会員企業においても次々と対策を講じております。しかし、これから僅か10年で25%削減という数値は、現状比50%以上の削減が必要ということになります。簡単に達成できる目標ではありません。
当連合会としては、オフィスビルの省エネ改修や最先端の省エネ技術を導入したビルの新設へのインセンティブを与える新たな制度の創設を国に強く働きかけていきたいと考えております。
また、わが国の大都市は、上海・香港・シンガポールといった都市との激しい国際競争の真只中にあります。
こうした視点に立って、国際競争力の強化に向けた「都市再生」を改めてわが国の経済成長戦略の柱に据え、不動産市場の活性化が図られるよう、訴えていく所存です。
2010年は、当連合会にとって、創立70周年という記念すべき年に当たります。業界の総力を結集し、健全で持続的なビル経営と活力ある都市づくりに取り組むとの決意を新たにしているところであります。
新年明けましておめでとうございます。昨年は住団連の活動に対して格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
リーマンショック以降の世界的な景気低迷の中で、厳しい年明けとなりました。今年の干支、庚寅(かのえとら)には、過去を省みて居ずまいを正し、良いものを継承しながら新しい形に変わるという意味があるそうです。心機一転、謙虚に事に当たり、力を合わせて良い方向へ向っていく時ではないかと思います。
さて昨年は政権交代という大きな変革がありました。新政権におかれては、厳しい財政状況の中で既成概念を打破した新たな切り口で問題解決に取り組んでいただいております。とりわけ、来年度税制改正においては、期限切れを迎える固定資産税の減税をはじめとする諸優遇策の延長が認められ、あわせて緊急経済対策の中で掲げられた住宅取得資金の贈与の非課税枠の拡大と住宅版エコポイント制度の創設など、住宅の建設に対して予算の配分をいただいたことは業界として大いに歓迎いたしております。内需主導型経済成長が求められている今、多くの産業に影響力のある、われわれ住宅産業の役割は非常に重要であると感じております。景気の二番底が心配される難しい時期ではありますが、引き続き適切な施策をタイムリーに実行していただき、景気回復への道筋を確かなものにしていただくことを念願いたします。
国民の暮らしの基盤である住宅・不動産を扱うわれわれの業界では、長期優良住宅の普及ならびに耐震改修やバリアフリー改修の促進等を通じて、豊かさを感じられる住環境の実現を目指して引き続き努力していかねばなりません。住まいは、個人の財産であるばかりでなく社会的な資産でもあり、質の高い住宅・住環境を提供することを通じて、より良い国づくりに関わっていることに誇りを持ちながら、本年も住環境の価値の向上に努めてまいりたいと思います。
その一環として、住まいに関わる方々が一堂に会して豊かさを感じる生活とはどういうものかについて考える「ゆとりある豊かな住生活を実現する国民推進会議」を行っておりますが、今年ですでに3年目を迎えます。住団連としては、この会議をより充実した活動にしていくことで、国民の住まいに対する意識を変革する原動力となるように積極的に働きかけていく所存です。会員の皆様のご支援ご協力をお願いいたします。
また、経済・金融の発展が、環境問題を抜きには立ち行かない状況が顕著になってきました。各地で気候変動に起因すると思われる災害も多発しており、温暖化対策としてのCO2削減は喫緊の課題です。
世界で年間273億トンのCO2が排出され、その50%未満しか自然界で吸収されないという現状を踏まえ、グリーン政策として省エネ、創エネのシステム導入が促進されておりますが、特に住宅業界に期待される役割は大きなものであります。エネルギー消費低減のために、住宅そのものの改善を図るとともに、住宅を取り巻く環境の整備にも努めなくてはなりません。住団連としても、新エネルギーの導入促進、建物単位の高断熱化、高効率設備機器の導入促進、という三本柱を効率的に組み合わせることで2010 年度に1990 年度と比較して建設段階でのCO2 を20%削減することを掲げておりますが、その目標に向けて住宅業界全体で取り組んでいきたく存じます。
「円高・株安・デフレ」という3つの問題を抱え、不透明な景況感の中スタートした本年ではありますが、より良いストック型社会の形成へ向けて努力することが業界に課せられた使命であり、その実現に向けて会員の皆様の一層のご支援を賜りますようお願いいたします。
本年が皆様にとりましても、業界にとりましても、素晴らしい一年になることを祈念いたしまして年頭の挨拶とさせていただきます。
新年明けましておめでとうございます。
賃貸住宅を取り巻く環境は、国土交通大臣の諮問機関である社会資本整備審議会の部会において議論されているように、国民の住生活における重要性の高まりとともに大きく変化しつつあります。
こういう時代こそ、賃貸住宅管理業者は、より高い倫理観を持ち、質の高い業務を通じて、借主に対しては安心・安全・快適な住環境を、家主に対しては健全な賃貸経営のサポートを提供することが、賃貸住宅市場の安定確保に繋がるものと考えております。
本年、当協会は管理業者である会員の自主ルールの策定に着手します。自主ルールは、倫理規定や業務報酬基準の策定、未収賃料の回収業務や預り金の分別管理のあり方など管理の基幹業務に対する自主的な高いハードルです。会員がこのルールを遵守し、より高度な業務を実現することは、借主・貸主を含めた社会全体に支持される賃貸住宅市場の構築に役立つことでしょう。
当協会は、賃貸住宅市場の整備と健全な発展のために全力を尽くします。皆様のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
あけましておめでとうございます。一般社団法人日本増改築産業協会を代表致しまして年頭に当たり一言ご挨拶申し上げます。
中国古典「大学」に次のような一節があります。
其の国を治めんと欲する者は、先ずその家を斎う。
その家を斎えんと欲する者は、まずその身を修む。
其の身を修めんと欲する者は、先ずその心を正しうす。
これを現代風に且私達に当てはめてみますと、お客様に信頼される協会にしようと思ったら、先ず会を構成する会員各社が、地域のお客様に心から信頼される会社にならなければならない。心から信頼される会社になろうと思ったら、社長が身を厳しく律しなければならない。それには先ず社長自身が心を正しくしなければならない。と言い替えることができると思います。
今、住宅業界は新築着工戸数の大幅な減少が何ヶ月も続いています。新築ほどではありませんがリフォームも厳しい状況です。このような経済情勢の中でも時代は粛々と進み、いよいよ我が国では住宅を堅固に作ろう、適切なリフォームをして、より長く住もうという方針が決定的になって参りました。私達リフォーム事業を営む者の責任がたいへん大きくなって来たということです。同時に新たなビジネスチャンスも増えてくるでしょう。だからこそ私達は事業を営む前に、人としての原点に戻り、己を厳しく律することを改めて考え実行する時であろうと思います。その上に立って様々な試みを積極的に展開する、ということが肝要ではないかと痛感しています。今年もどうぞよろしくご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。
「インテリア産業界の信頼を勝ち得るために厳しい環境に立ち向かって」
明けましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。
今年もよろしくお願い申し上げます。
昨年5月、会長に就任して8ヶ月が経過しましたが、不慣れな中でのスタートにあたって、関係者の方々の大変なご尽力を賜りましたこと厚くお礼を申し上げます。
さてインテリア業界を取り巻く環境は依然として低迷状況にあり、予断を許さない局面にあると認識しています。私は会長に就任して以来、この重責を果たすために前例に捉われることなく、ごく基本的なことを時には思い切って大胆に、時には小さなことを着実に実行したいと考えてきました。
また、インテリア業界が発展していくためには、当協会に加盟している各企業が発展していくことが基盤にあって、そのためには企業もCSR(企業の社会的責任)があるように、業界としてのCSRも必要になると思っています。業界を活性化していくためには、各企業が成長すること、共通の理念のもとに、何より業界が団結して、知恵を結集し、困難に立ち向かうべき時だと考えます。
昨年、お陰さまで当協会は創立30周年を迎えました。改めて、次の40周年、50周年に向かって基本方針を定めて、目的達成のためにレールを敷くことが私の責務であり、地道な活動をしていきたいと思っています。
当協会は5委員会を組織して活動していますが、これまで推進してきた事業の再点検による見直しも必要になるかもしれません。
新しい年を迎え協会として協会員として、新鮮なトレンドを打ち出し、生活者に向けて豊かな住空間の提案、少子高齢化社会でのやさしい確かな製品づくり、環境に配慮した製品づくりといった商品開発や、健全な競争による流通の合理化、国際見本市としてのJAPANTEXなど、しなければならないことが山積みです。
まず具体的には協会の5委員会活動の活性化です。そのひとつが今年第29回を迎えるJAPANTEX2010です。
JAPANTEXは運営を外部委託しないで、会員企業から委員を選出して実行委員会を組織、運営するまさに手づくりの展示会です。昨年のJAPANTEXは、3日間開催、対象をBtoBに徹して開催しました。JAPANTEXは今年で29回を迎える歴史ある展示会です。
展示会のあり方が変化しつつある状況の中で、昨年のJAPANTEXを検証して、出展者にも来場者にも満足していただけるJAPANTEXを目指して、インテリアファブリックスを核(コア)としたインテリア総合展示会を再構築していきたいと思います。
流通合理化委員会では、IT環境の整備がもたらす効用を追求しています。具体的にはデータベース構築による利用者への利便性向上に取り組んでいます。インテリアシミュレーションシステムなどもさらなる精度向上がテーマです。
需要開拓委員会では、昨年「4月10日はインテリアを考える日」を再始動させ、シンボルマークを募集し制定、さらには「毎月10日はインテリアを考えよう」キャンペーンを打つなど積極的に展開しています。こうした活動が浸透することで、少しでも需要の喚起につなげていきたいと思います。また物性マークの浸透(遮光、防炎、制電、ウォッシャブル、はっ水)も推進していきます。
環境技術委員会では、「環境」という大きなテーマに取り組んでいます。インテリアファブリックスが消費者にとって、安全でやさしい製品になるように調査・研究はもとより、関連団体との連携(ホルムアルデヒド放散自主基準、カーテンの難燃剤HBCD使用削減計画、グリーン購入法など)によって、各種規制基準づくりの動向に適切に対応していきます。
調査・人材育成委員会では、企業の新人・中堅社員に向けての講座・セミナーなどを通じて人材育成をはかっていきます。また毎年、「インテリアファブリックス事業の概況・市場規模の策定」を発行しています。これらも着実に進めてまいります。
年頭にあたって、推進項目、課題などさまざま列記しましたが、ひとつひとつ確実に進めていくことが必要だと思っています。これらの問題・課題は私に課せられた、またインテリア業界と当協会に課せられたものと重く受け止め、業界発展のために頑張っていく決意を以って年頭のあいさつと致します。
関係各位のご多幸とご健勝を心よりお祈りいたします。