

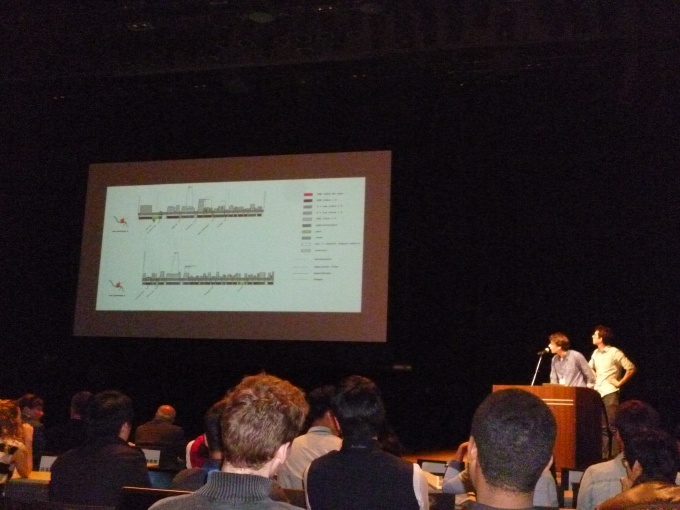
慶應義塾大学をはじめフランス、イタリア、中国、韓国の8大学によるシンポジウム「グローバルな視点から見た東京・日本橋の都市環境」が15日、日本橋三井ホール(東京都中央区)にて開催された。
同シンポジウムは、国際大学連携による建築デザイン演習の共同授業プログラム「AIAC ( L'Atelier International de L'Architecture ) 国際建築スタジオ2013」の1次ワークショップ成果発表の場として行なわれたもの。
AIACは、2000年から毎年世界各地で開催しているプログラムで、世界各国の大学が共通のテーマと条件で、共通の対象敷地について大学ごとに架空のデザインを提案しアイディアを競う。
今年度は、「東京・日本橋」を対象テーマに、パリ・ラビレット国立建築大学区(フランス)、ヴェネツィア建築大学(イタリア)、清華大学(中国)、ハルピン工業大学(同)、瀋陽建築大学(同)、慶尚大学(韓国)、漢陽大学(同)と、初参加となる慶應義塾大学の計8大学約100名が参加している。主催は慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科環境イノベータコース、協賛は三井不動産他。
参加校は4月10日から15日の6日間にわたる本ワークショップの間、日本橋に関する資料収集や現地調査・聞き取り等を実施、各校ごとにプレゼンテーション資料を作成し、同シンポジウムに臨んだ。
シンポジウムは2部構成。第一部では、「世界の大学生が見つけた東京・日本橋」と題し、各大学が持ち時間20分で調査分析結果と初期提案発表を行なった。第二部は「国際的環境先進都市の象徴としての日本橋」と題し、参加校の教授4名が講演した。
各国の学生からは、川や河川敷を活かした都市環境づくり、首都高速を取り除いた空間づくり、首都高速の一部を活用したイベントスペース創出、伝統を維持しながらの都市づくり等、日本橋をテーマにさまざまな提案が出された。
また、日本橋については、「路地に面して歴史ある老舗等の建物が立ち並び雰囲気がいい」「東京の中心でありながら静か」のほか、「まちのシンボルがない」「休憩する場所がない」などの感想が語られた。
関心が高まっている首都高速については、「視野が遮られ空が見えない」「水路が見えない」といった批判的な見方もある一方で、「グーグルマップでは分からなかったが、現地で見ると存在感が大きい」「首都高がつくられた時代の日本の活力を感じる」「東京の歴史、成長、都市化のシンボル」「モニュメントとして残す価値もあるのでは」との認容派の意見も出た。
9月にパリのユネスコ本部で2次ワークショップが開催され、参加学生が最終的な成果を発表。優秀な作品は表彰される。



