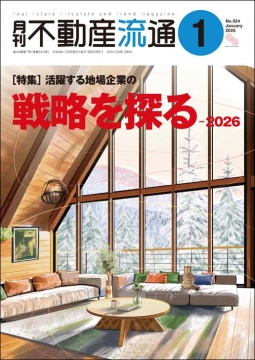宮城県気仙沼市、その凄まじき津波被害
東北地方太平洋沖地震発生から1ヵ月が経った。東日本一帯に被害をもたらした未曽有の大災害は、その全容がほとんど解明されていないが、多くの読者の脳裏には、マグニチュード9.0という巨大地震そのものではなく、それが巻き起こした「津波」の恐怖が焼きついているのではないだろうか。 記者は、4月上旬、その津波の直撃を受けた、宮城県気仙沼市に入ることができた。市街地の3割、約480haが浸水したという同市。そこで目にしたものは、「人知を超えた天災」の一言では済まされない、凄まじい津波の痕跡と、そこから立ち上がろうとする住民の姿だった。

















瓦礫の山、汚泥が残る道路…被災地に入る
当欄を読む人に、知っておいていただきたいことがある。不快に思う人もいるだろうが、勘弁していただきたい。
記者は、気仙沼に入ると決まった時、ある決意をした。それは「被災者の悲惨さを強調する一般マスコミのような報道は、絶対にしない」こと、そのうえで「一般マスコミが報道しない建物の破壊状況を克明に見てくる」ことだ。無論、被災者の苦しみからは目を反らしてはいけないが、安っぽいセンチメンタリズムは排し、見たままの建物被害を淡々と記そうと思った。
一目、現地を見るまでは…。
◆ ◆ ◆
仙台から東北自動車道を北上すること1時間30分。記者の乗った車は、一関インターチェンジを降り、太平洋を望む気仙沼市に向け東上を始めた。トランクには、地元の不動産仲介会社に届ける救援物資が詰まっている。今回の取材は、この救援物資を届けるグループ会社に同行することで実現した。
春らしい日差しの中、田舎道を淡々と走る。途中、救援車両何台かとすれ違ったものの、地震の被害はほとんど目にしなかった。それは、気仙沼市に入っても変わらず、記者もやや緊張感が解けてしまった。配給物資を抱えて歩く住民の姿は時々見かけるものの、まちや建物への被害はまだ確認できなかった。車内から見る住宅は、普通に人が住んでいる。商店は普通に営業している。
高速を降りて1時間。ようやく、三陸海岸を縦断する「気仙沼バイパス(国道45号線)」に行き当たる。この先の湾岸部が、同市の中心地だ。そして、この道路を越えた途端、まちの姿が一変した。
バイパスの至る所には、ぐしゃぐしゃに壊れた車が何台も放置されていた。車の窓は閉め切っていたが、車内に潮の香りと埃が充満し始め、タイヤノイズが大きくなり、車体が細かく震えだした。整備されたとはいえ、道路上には汚泥がまだ残っているのだ。
バイパス周辺の建物は壊れていなかったが、壁を見ると床上50~80㎝あたりに、泥のラインが入っている。その高さまで津波で浸水した証だ。ただ、この辺りでは、どの建物も破壊は致命的ではないようだ。室内の泥を淡々と掃き出す住民。この程度の浸水で済んだのは、むしろ幸運な部類なのだろう。
バイパスを渡ると、被害の深刻さの度合いは、さらに増してくる。建物はまだ残っているが、道路は大量の瓦礫で溢れており、それらを避けながら車を慎重に走らせる。瓦礫と化した建築物や車の量を考えれば、震災後1ヵ月足らずでここまで道路が使えるようにした、住民や救援活動従事者の努力には、ただただ脱帽するしかない。
浸水・破壊され尽くした建物。それでも住民は…
車を降りて、まちを歩いた。
建物の1階部分は完全に浸水し、なかには2階部分まで浸水しているものもある。窓ガラスが木っ端みじんに破壊され、中が丸見えの家も多い。ある家では、垣根に囲まれた庭いっぱいに車が鎮座していた。津波で流された車が庭に「はまっている」のだ…。
そんな建物の中で、住民たちは黙々と後片付けしている。家の前の瓦礫と家を往復し、ただひたすらに、新たな瓦礫を積み上げていく。そんな光景が、至る所で繰り広げられていた。もはや「住まい」としての機能は完全に失われているはずだが、それでも住まいを、そしてここでの生活を捨てることができない。そんな住民の気持ちを思ったとき、カメラのファインダーが曇った。
木造アパートを見つけた(後で調べたところ、築21年だった)。1階住戸のサッシュは完全に破壊され、室内を津波が渦巻いたようだ。玄関側は比較的きれいだったが、2階外階段と廊下を支える鉄骨はたわんでおり、津波のエネルギーを物語る。
瓦礫の傍に、住民のものらしき、泥まみれの小学校卒業文集が落ちていた。「山口百恵」「あいざき進也」などが出てくるから、持主は記者より若干歳上、もう50過ぎだろう。はたして無事に避難できたのだろうか?
基礎からえぐり取られた住宅。飴のように曲がる鉄骨
車に戻り、市内を縦断する大川沿いに、下流に100mほど下った、河口から3kmほど上流にあたる住宅街に入る。今回、救援物資を届けた不動産仲介会社の事務所があったエリアだ。海風に煽られた砂塵が舞い、汚泥の放つ異臭がさらに濃くなってくる。川の向こう側は、まだ許可証なしでは入ることができないようだ。
その理由はすぐに分かった。わが目を疑う光景が、広がっていた。あるべきはずの「まち」が消えていた…。
しばらく身体が震え、茫然と立ち尽くした。
3月11日のその時、この場所で、建物とともに、家族や生活までも津波に呑みこまれていった人たちを思うと、建物を冷静に観察することも、シャッターを押すことも容易にできなかった。なんとか己を奮い立たせ、嗚咽を押し殺しながら、夢中でシャッターを切り、まちを歩いた。
残っている建物は、1ブロックにせいぜい1、2棟。あとは建物が「あった」ことを示す瓦礫の山と住宅の基礎が延々と続いていた。それらの建物も、2階部分まで破壊しつくされ、もはや「建っている」だけ。築年が浅いと思われる鉄骨造の戸建住宅も、サイディングボードはボコボコ穴があき、断熱材や鉄骨がむき出していた。大型トラックが飛び込んでいる住宅や、基礎がほとんどなくなっている場所(住宅)もあった。魚市場か倉庫の巨大な建物は、鉄骨の太い骨組みを除き、壁がすべて破壊され、その骨組みも飴のように曲がっていた。誇張することなく、昔社会の教科書で見た「東京大空襲後のまち」を想起した。
阪神・淡路大震災後の住宅街を歩いたときも、瓦礫と化した住宅を数多く見たが、それでも建物の基礎はしっかり残っていた。基礎までえぐり取る津波のエネルギーとは、一体どれほどのものなのだろう…。だが、残っていた建物の何件かで、普通に室内に人がいたのには驚いた。ある家では布団や畳を干し、ある家ではガラスがすべて割れた居間の奥で、家主がたばこをくゆらせていた。
「ここから海が見える。まちの形が変わった」
大川には、車はもちろん、どこからか流れ着いた戸建住宅が、無残な姿のまま、静かに浮かんでいた。その屋根で、海鳥が呑気に鳴いている。澄んだ青空と海鳥の声と、目の前に広がる光景とのあまりのギャップに、また涙が込み上げてきた。
不動産会社の事務所があるという場所は、ただ瓦礫が山のようにあるだけだった。K社長と家族、従業員は幸いにも難を逃れ、管理物件の一室に事務所を構え、営業を再開していた。
「ここ(津波の被害がなかった街道の山側)から海が見える。管理物件もみんな流された。うちの事務所も、仲間の事務所も流された。まちの形が変わってしまった…」。努めて明るく話してくれたK社長だが、その言葉は、自然の猛威に抗うことのできない無念さで溢れていた…。
それでも、被災者のため、まちのために、歩みを止めるわけにはいかない。「全国の宅建協会の仲間も支援してくれる。事務局から、パソコン2台をいただいたので、地元の仲間たちにも契約書面や資料を打ち出してあげることができる」、こう語るK社長の顔は、素敵な笑顔だった。取材中も、ようやく開通した電話が鳴り止むことはなかった。
店内を津波が突き抜けたとおぼしき靴屋の前を通った。店はがらんどうで、店頭に大量の靴が、無造作に山積みになっていた。無論、泥だらけで売りモノにはならないだろう。
その靴の山を住民が取り囲んでいる。よく見ると、山の中から左右揃った靴を器用に探し出し、海水で洗っていた。住民にとっては、たとえ汚泥が染みついていても、まだまだ靴は貴重品なのだ。普通の生活を取り戻すためには…。
わずかな標高差が、住民の運命を決めた
気仙沼バイパスを、仙台に向かった。進行方向左手(湾岸部)は瓦礫と破壊しつくされた建物、道路の周りは折れた電柱、切れた電線、浸水し流されてきた車という光景が続く。自衛隊や消防・警察といった緊急車両が、一般車両を圧倒していることからも、このまちがいまだ「有事」にあることを理解させてくれた。標高が低いエリアでは、時折瓦礫がバイパスを越え、山側にまで流れ込んでいた。ほんの少しの標高差が、人々の命運を分けたようだ。
高台の公共駐車場に車を止め、眼下に海沿いのまちを眺めた。大量の瓦礫と土砂に埋め尽くされたそこは、すでに「まち」ではなかった。建っている建物も根元は例外なく土砂に埋まり、元来建っていた場所にあるかどうかは見分けられなかった。海沿いを走っていたJR気仙沼線の線路はぐにゃぐにゃと曲がり、コンクリートの橋脚は、根元から綺麗に折れていた。
湾岸から続くまちなみにカメラを向けたとき、瓦礫の奥で深緑の影が動いていた。自衛隊だった。数人がかりで、見るからに丁寧に、瓦礫を手でどけていた。「何をしていた」のかすぐわかった。ズームするのを止め、心の中で手を合わせた。
◆ ◆ ◆
気仙沼では、人も、そして建物も、まだ「死」と隣り合わせだった。だが、そんななかでも、出会った人、見た人はみな、黙々と逞しく、前を向いて「生きて」いた。
このまちがよみがえるには、気が遠くなるほどの時間がかかるだろう。途方もない費用もかかるだろう。それでも、住民の多くは、このまちを離れるという選択はしないと、記者は確信できる。1000年に一度といわれる大津波も、まちを愛する人々の想いまでは、打ち砕くことができないはずだ。(J)