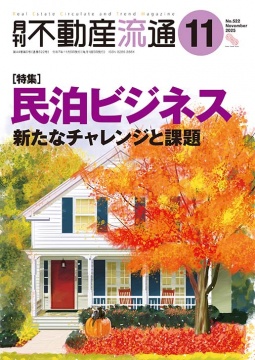震災で発生した小さな被害と大きな悩み
3月11日に発生した東日本大震災。甚大な被害をもたらした未曾有の災害は、発生地から遠く離れた関東にもさまざまな爪痕を残した。液状化により大きな被害を受けた物件がテレビなどで報道されたが、それ以外にも、軽微な損傷も含めれば、何らかの影響を受けた物件は相当数にのぼるのではないか。 東京都内某所のあるマンションでは、躯体などには被害がなかったものの、窓ガラスに多数のひびが入る被害が発生した。 この修繕をどうするか、管理組合主催の説明会が開催されるとのことで、潜入取材を敢行した。その時の様子をレポートする。




全戸すべての窓を二重サッシに
該当物件は東京都23区内に所在する、8階建て、築37年のマンション。いわゆる旧耐震物件だ。全67戸のうち25世帯で窓ガラスにひびの入る被害が発生。その数、38枚に及んだ。ちなみに何階に多く発生、あるいはある方向に多く発生などの傾向は確認できず、順不同とでも言おうか、被害は各方向ばらばらに発生したという。
当初は、ひび割れた窓ガラスの修理について、該当戸所有者の自己負担とするか、管理組合が修繕積立金で補修するかで検討が進められたというが、「震災前に実施した区分所有者アンケートで、窓などの開口部についての不満・不具合が多数確認されていたので、さらに一歩進めた案について検討することにしました」と語るのは、同マンションの管理組合理事長を務める平賀功一氏(e住まい探しドットコム主宰)。
その案とは、全戸の外窓をサッシごと交換するというもの。これを含めた今回の対応について、総会で決議する方向で話を進めるという。その前段として、区分所有者、入居者向けの説明会を開催したのが今回の集まりだ。
今回の説明があった外窓交換の方法は、元のサッシ枠はそのまま活用、新しい枠をカバーしてサッシ・窓を丸ごと刷新するというもの。既存物件での改修方法として、現在主流となっている方法である。
その際、複層ガラス(二重サッシ)にすることで、断熱性、遮熱性、遮音性のほか、耐風圧性、機密性、水密性(雨を伴った強風の時に、サッシから室内に雨水が入らない性能)の向上も見込まれるという。
また今回は、現金による支払いの他に、リース方式についても説明があった。
ここでマンションの共用部分改修をリース方式で提供するサービスについて簡単に説明したい。多額の費用負担が必要な共用部の修繕について、リース会社が最長10年でリース契約するというもの。所有権はリース終了後に管理組合へ無償で移転される。多額の現金の用意が不要で、動産保険が付保されるなどのメリットがあるため、今多くの管理組合の注目を集めている。
このサービスについては、三協立山アルミ(株)とオリックス(株)、(株)LIXILと三菱UFJリース(株)がすでに開始しているが、歴史は浅い。
今回のケースでは、マンション全部の窓ガラス(はめ殺しを除く)を交換したとすると、5年リースで一世帯あたり約5,500円/月、10年リースで約3,000円/月という試算であった(工事費は別途なので修繕積立金から拠出予定。本物件では約800万円)。
築20年超のマンションに住み、結露に悩む記者は、「この話はすぐにまとまるだろう」…と思っていたのだが…。
気になるマンションの「寿命」
出席者の反応は、正直今ひとつだったのた。その要因は主に「交換のデメリット」と「本マンションの寿命」にあるように感じた。
「交換のデメリット」として大きいのが、ガラス面の縮小だ。もとある枠新しい枠を入れ込む手法ゆえ、どうしても現在の枠より狭まってしまう。従ってガラス面も縮小してしまうのだ。
もともと最近主流のマンションのように開口が大きくとられていないないため、ガラス面が縮小することに抵抗を覚える人が多いようであった。
もう一つの「本マンションの寿命」。これは大きなハードルだろう。ある出席者が放った「うちのマンションは、あとどのくらいで建替えなのですか?」。この問いに集約されている。
「建替えをするのなら、今窓を交換したらもったいないじゃないか。いつ建て替えるのか?」。確かにそのとおりである。
しかし建替え決議はそう容易ではない。建替えに向けての話合いも始まっていない今、建替え時期は誰にも分からないのである。
このマンションでも、多くのマンションがそうであるように、規約で「窓枠・窓ガラスは専有部分ではない」「窓ガラスなどの改良工事は、管理組合が計画修繕として実施する」と定められている。
故に、現在、ひびの入った窓ガラスの部屋の入居者は勝手に修理するわけにもいかず、段ボールやガムテープで応急処置をして住んでいるような状態なのだ。
「とりあえず、ひびの入った窓ガラスは管理組合のお金でガラスを入れ替えるのがいのでは」。そんな意見ももちろん出た。
どの案もメリット・デメリットがあるため、なかなか組合の総意としてまとめるのは難しそうであった。
結局この日の説明会では、「修理に留めるか、刷新するか、刷新するにしてもガラスは単板か復層か、現金拠出するかリースかなど、選択肢が多いので、またアンケートをとるなどして分かりやすい方向で練り直す」との理事長のコメントで一旦お開きとなった。
合意形成の難しさ
(社)高層住宅管理業協会が全国の会員社に対し実施した東日本大震災の被災状況のアンケート結果では、8万5,798棟中、大破は0棟、中破は61棟と多くはなかったものの、小破は1,070棟にのぼった。ここには今回取材したマンション程度の軽微な損傷は含まれないので、もしそういったマンションもカウントしたら相当数にのぼるであろう。
そのいずれもの物件で、今回のような話合いが進められていることは容易に推察できるし、そしていずれの話合いも話をまとめるのは容易ではない。
今回サッシの交換案を提案した住宅資材会社曰く、「これまで今回のような提案を100以上の管理組合に提案したが、受注につながったのは2割に満たない」とのことであった。
また、あるインスペクション会社には、震災後たくさんのマンションから調査の相談が寄せられたそうだが、検査を受けるか受けないかだけでも話がまとまらない管理組合が多いという。そこからさらに修理・修繕となると、さらに合意形成は難しくなる。
インスペクション会社の社長は、「今後、マンションの修理・修繕に関して、合意形成がまとまらず、話が進まないといった問題が表面化してくるのではないか」と危惧していた。
マンションにおける合意形成の難しさは以前から指摘されている。「たまたま同じマンションを買った人の集まり」である管理組合に、それをまとめろ、というのは酷な話だ。
マンション管理士・管理会社のバックアップ、決着しやすい仕組みづくりなど、業界あげての支援が必要ではないだろうか。(RN)