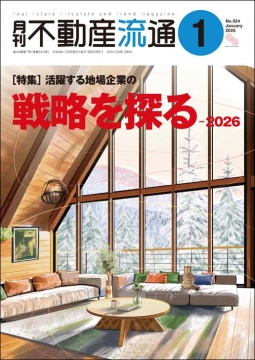アメリカの大晦日は賑やかだ。ホテルのパーティーはダンスフロアにカップルがあふれ、夜中12時が近づくと「蛍の光」が演奏され秒読み開始。全員がドラムと共に声を合わせ、10秒、9秒、8秒…、とカウントダウン。
12時だ!
抱き合いキスをし、「ハッピィニューイヤー!」
誰もが音の出るオモチャを手にして、たたいたり笛を吹いたりクラッカーを鳴らして陽気に新しい年を祝う。
しかし、初日の出を拝んだり神社へお参りに行って願をかけたりおみくじをひく正月の行事は皆無である。アメリカには「お正月」の習慣はないのだから。1月1日は祝日で休みだが、2日からは仕事が始まる。
願いを叶えるにはどうする?
流れ星に3回願いを掛けるとか、バースディケーキにろうそくを立てて願いをこめて炎を吹き消す…、その程度しか思い付かない。「願って掛ける?」とアメリカ人の友人達に聞いたところ、大半は「NO」であった。
例えば、大学入試についていうと「合格祈願を紙に書く暇があったら、ノートをひろげて勉強したら?その方が合格の確率は高いはず。」結婚も「神様に祈るよりネットで調べる方が早いでしょ?」なるほど…。
「教会に礼拝に行った時にフットボールチームの優勝を祈った」と言う友人はいたが、家族や友達の病気回復の願いなどとなると、カードや花を本人宛に送る人が多い。自分の気持ちを直接相手に伝えるのが現実的だ。
日本人なら一度は経験する「願掛け」
そもそも「願を掛ける」とはどういうことなのだろう?
元来は、逆境を打破して願いの実現に向けた精神的な決意を得ようとする真剣な行為で、願望を実現させるために神仏に誓いを立てる。病気治癒や商売繁盛、縁結びや厄払い、昔は雨乞いや豊作祈願などの願かけもあっただろう。
病気回復や平和を祈って折鶴はしばしば飾られるし、願いがかなうまでお酒やタバコ、好物を断つ人もいる。お百度詣りとか水ごりなども昔は行なわれていた。神社でおみくじをひいて、その年の運勢を占ったり、傍らに設置してある木々に結びつけ、大学入学や就職、結婚な、ど願いが叶った時はもう一度神社に行ってお賽銭をあげ、成就に対して神様に感謝する。多くの日本人は経験があるはずだ。
「願掛け」アートがアメリカで話題に
その日本の「願掛け」に感銘を受けて、アーティストの友人が作品を制作、発表した。
アメリカのある大学のキャンパスや町で、人々に「何か願いを書いて欲しい」と願かけ用の紙片を人々に渡して、沢山集まった願い事を日本の神社で見かけるようにひとつひとつ折ってギャラリーの壁いっぱいに展示したのだ。日本では日常見慣れている光景だが、アメリカでは物珍しく、コミュニティ・アートとして話題を呼んだ。
願かけの紙片は無記名で、年齢も性別も不詳。折ってあるので書いてある内容は当然ながら読めないが、あとでこれらの「願かけ」を友人からそっと見せてもらって驚いた。「孤独すぎる」「お金が欲しい」「死にたい」さらに「誰かを殺したい」など物騒な願かけもあって、その内容の深刻さに考え込んでしまった。
大自然や神に対する謙虚さの現れ
それにしても、アメリカ人は全く願を掛けないわけではない。キリスト教では、教会でいつも信者は神に願いを込めて祈ることができる。カソリックの教会では願いを込めて信者達が灯明をあげ、沢山のあかりが美しく揺らめいている。ユダヤ教でも家族や友人の病気の回復を祈り、願掛けをする習慣があるそうで、律法師に病人の名前をヘブライ語で読み上げてもらい、会堂に集まった人々全員で心を合わせて回復を祈る。イスラム教とヒンズー教はよく知らないのだが、宗教に基づいた願掛けも祈りもあるに違いない。
これらの「願掛け」は、信者が自分の属する宗教に従い祈る行為である。だから日本のように神社でおみくじをひき、寺で小銭を賽銭箱に投げ入れて願をかけ、教会で賛美歌を歌って神様にお願いを、というざっくばらんな行動は外国人にとって理解し難いようだ。
日本人の宗教観となると別のテーマとなろうが、少なくとも「願掛け」に絞ると「神に願いを託す」という行為には、人の力以上のもの、大自然や神に委ねる人間の謙虚な気持ちが存在しているように思う。
「願掛け」は、日本をはじめとして多くの国々の歴史を通して見られるし、現在のアメリカでさえ見出すことができると感じている。
Akemi Cohn
jackemi@rcn.com
www.akemistudio.com
www.akeminakanocohn.blogspot.com

コーン 明美
横浜生まれ。多摩美術大学デザイン学科卒業。1985年米国へ留学。ルイス・アンド・クラーク・カレッジで美術史・比較文化社会学を学ぶ。
89年クランブルック・アカデミー・オブ・アート(ミシガン州)にてファイバーアート修士課程修了。
Evanston Art Center専任講師およびアーティストとして活躍中。日米で展覧会や受注制作を行なっている。
アメリカの大衆文化と移民問題に特に関心が深い。音楽家の夫と共にシカゴなどでアパート経営もしている。
シカゴ市在住。