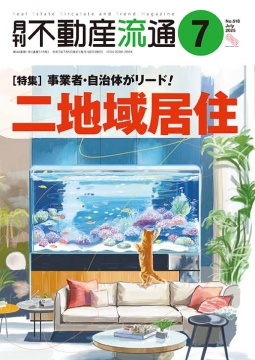マレーシア第1の観光地、マラッカの歴史は15世紀のマラッカ王国まで遡ります。その歴史的価値から、2008年にはマレーシアで初めてユネスコの世界文化遺産に登録(※)されました。
東西貿易の要衝・マラッカ

帆船時代、インド洋を渡る商船は季節風を利用して、冬は北東から南西に向けて、夏は南西から北東に向けて針路を取りました。海峡に面するマラッカは、風向きが入れ替わるのを待つ間も交易に便利な場所で、インドや中国、遠くアラビア半島から商人が到来。16世紀にマラッカに来たポルトガル人トメ・ピレスは、「62ヵ国の商人が集まり、64の言語が使われていた」と、その繁栄ぶりを記しています。

|

|
明の庇護で発展
その発展の歴史には、中国・明の存在が大きく関わります。1405年、明の永楽帝は鄭和に命じ、7回にわたって南洋に大艦隊を派遣します。1498年にインド航路を開拓したヴァスコ・ダ・ガマよりも早く、インド洋を航海した艦隊の寄港地がマラッカでした。マラッカ王国は明に朝貢して庇護を受け、中国南部から移り住む人が増加しました。

トコン通りにある「青雲亭(チェン・フーン・テン)寺院」は、鄭和の業績を記念して1646年に建立されています。建築資材や仏像なども中国から運んだもので、陶器で彩られた屋根や重厚な装飾に当時の中国人職人の高い技術が発揮されています。
ポルトガルによる占領

早くから海外進出を図ったポルトガルは、1511年にマラッカを占領します。市街を見下ろす「聖ポールの丘」に「サンチアゴ砦」を築き、外敵からの防衛に当たりました。

丘の裏手には、1521年にポルトガルが建造した「聖ポール教会」の跡も残っています。フランシスコ・ザビエルは、ローマ教皇の命令により、キリスト教伝道のためにマラッカに来ました。イエズス会の拠点だったインドのゴアとマラッカを往復するうち、日本人アンジローに出会って、日本に向かうことを決意したと伝えられています。

オランダ広場からマラッカ川に沿ってバンダ・カバ通りを歩くと、「聖フランシスコ・ザビエル教会」があります。ザビエルを顕彰するため、1849年にポルトガル人の子孫が建造したもので、ステンドグラスが美しいネオ・ゴシック建築の建物です。
植民地時代の建物が集まる「オランダ広場」
オランダ広場にある「スタダイス」は1650年建造、東南アジアで最古のオランダ建築の一つです。古いオランダ語で“市庁舎”という意味で、オランダ東インド会社の拠点でした。現在はマラッカ歴史民俗博物館になっています。
スタダイスに隣接する教会は1753年建造で、オランダのマラッカ統治100年を記念して建築されたもので、一本の木からできた高さ30メートルの梁は建築当時のままです。
東南アジアにおける熾烈な覇権争いで、ポルトガルがオランダに敗れると、オランダは各地でイギリスと衝突。勢力争いが激化したことから、マラッカ海峡を境に両国の勢力範囲を定めた英蘭協約が1842年に結ばれ、マレー半島はイギリスの支配下に入ります。
社交クラブだった「独立宣言記念館」

オランダ広場からパラメスワラ通りに向かうと、2階建てのクリーム色の建物が見えます。在住イギリス人たちの社交クラブ「マラッカ・クラブ」の会館として使われた建物で、現在は「独立宣言記念館」として独立に至るまでの歴史が展示されています。
英領になったマレー半島は、アジア・太平洋戦争中に日本に占領され、1945年の日本の敗戦後、再びイギリスの統治下に入ります。後に首相になる“建国の父”アブドゥル・ラーマンはイギリスとの交渉を進め、1956年2月、マラッカで独立を宣言しました。マレーシアは翌1957年8月31日に悲願の独立を果たします。
東西交易の要衝にあったマラッカ。港町を通り過ぎていった国々の影響は、土着の文化と融合して、今もマラッカ独特の言語や料理、建築物などに残っています。
※ジョージタウンと共に「マラッカ海峡の古都群」に登録

森純(もり・じゅん)
文筆業。出版社・広告代理店などで書籍・雑誌の編集を担当、現在はフリーランス。衣食住など人の暮らしぶりに関心があり、日本と東南アジアを往還しながら複数拠点生活中。「海外書き人クラブ」会員。