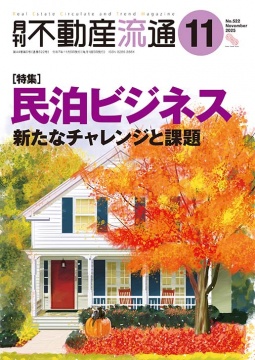(一財)不動産訂正取引推進機構(RETIO)は19日、2015年度第1回「不動産経済分析研究会」の議事概要について公表した。
11年5月に不動産価格指数(住宅)の作成に関する国際指針(Handbook on Rsidential Property Price Indices)が作成されたことを受け、日本でも関係省庁と連携した国際指針に基づく不動産価格指数(住宅)の開発、本格運用等が行なわれている。一方、日本の不動産市場の透明性、投資環境の充実に関する政策課題についてさまざまな指摘があることから、同機構において不動産経済分析研究会を開催。有識者からのヒアリングを通じ、安全な不動産取引の確保、不動産市場の安定を妨げる政策課題、改善策、研究テーマについて把握し、今後の研究につなげていく。
第1回目のテーマは「不動産市場の透明性向上に向けた不動産価格指数の整備に関する動向」。同機構主査でシンガポール国立大学不動産研究センター教授の清水千弘氏が講演した。不動産価格指数に関する経緯と現状について、07年のサブプライムローン問題、08年リーマン・ショック等の不動産市場を契機にした世界的な金融危機の発生から、多数の国際機関が協力し11年5月に不動産価格指数に関するハンドブックが作成されたこと、商業用不動産についても本年末までにガイドラインが公表される予定であることなどを説明。また、日本においても、国土交通省が中心となり、「不動産価格の動向指標の整備に関する研究会」を発足、不動産価格指数(住宅)が本格運用し、集合住宅に関する指数も東京のデータで大枠ができ上がっていることを説明した。
また、ゲストスピーカーのMSCI Icn.東京支社不動産サービス日本市場責任者の鈴木英晃氏は、同氏はMSCIについてその沿革や特色などを説明。日本における政策課題として、インデックス・ベンチマークの定義を明確にした上での議論や、官民一体となった市場透明性への向上連携、グローバルな視点での情報透明性の向上、不動産投資家の団体がなく、投資家の声を直接政策に反映しにくい点などを指摘した。
(株)野村総合研究所上級研究員の谷山智彦氏は、国土交通省は年間約30万件の不動産取引価格情報に基づいた指数を数値化した「不動産価格指数(住宅)」を、住宅と商業用不動産を分離させ、取引から約3ヵ月後に指数を推計・公表していること、不動産価格指数の分析手法は国際ハンドブックに準拠した推測方法であるヘドニック・アプローチを採用していること、無数の不動産インデックスが官民で提供されているが情報の「偏在」と「遅延」により、利用者にとってかなrずしも利便性の高い指数となっていないことなどを説明した。
今後2ヵ月に1回のペースで不動産経済分析に関わる有識者の講演や意見交換を行ない、その趣旨について当機構機関誌等で紹介する。15年度においては、市場の透明性の確保、市場分析手法等の不動産経済分析おける、政策課題、今後の研究テーマを整理する。