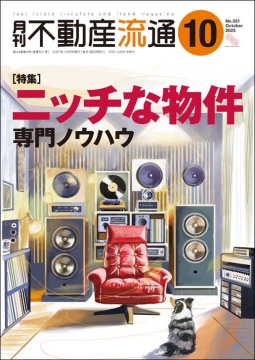社会資本整備審議会住宅宅地分科会の「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」(委員長:浅見泰司東京大学大学院工学系研究科教授)が19日、初会合を開いた。
新たな住生活基本計画に盛り込まれた「住宅確保要配慮者の増加に対応するため、空き家の活用を促進するとともに、賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた、住宅セーフティネット機能の強化」の実現に向け、課題の整理や制度の基本的方向性を定めるのが目的。
会合では、低額所得世帯や高齢者世帯、生活保護受給世帯の増加、若年世帯の住居費負担割合の増大、住宅確保要配慮者に対する入居制限などの現状に対し、公営住宅の管理戸数が頭打ちであること、公営住宅の応募倍率が大都市圏を中心に高水準である現状を説明。公営住宅や民間住宅を活用した住宅確保要配慮者向け賃貸住宅制度(借上公営住宅、地域優良賃貸住宅、あんしん居住推進事業住宅)を補完する新たな仕組みを、増え続ける空き家や民間賃貸住宅ストックを活用し、生活保護受給者や低額所得者、障害者などに限定せず、若年世帯や多子世帯など多様な住宅確保要配慮者も対象に構築することを基本的な方針とした。
具体的には、住宅セーフティネット機能を持つ民間住宅を、家賃債務保証を引き受ける事業者情報なども含め、地方公共団体に登録、入居希望者に情報を提供するといった仕組みをイメージ。地域の実情に応じ、地方公共団体が家賃補助額等を柔軟に設定できるようにする。オーナーの不安を解消するため不良入居者や家賃滞納者への対応ルールやトラブル解決の仕組みづくり、不当に入居拒否されないための仕組みづくり、家賃の低廉化や改修への支援措置、登録住宅に係る税制支援、住宅確保要配慮者に対する入居支援やサービスを行なう居住支援協議会等との連携などについて、検討を進めていく。
また、(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会からは、高齢者・低所得者・貧困世帯向けの住宅を、民間賃貸住宅に差額家賃を補助することで実現する「セーフティネット住宅」と、若年夫婦や子育て世帯などの生産性を向上するため、子育てが円滑に行なえる民間賃貸住宅への差額家賃を補助する「ステップアップ住宅」の構想が提案された。
参加した委員からは「どこまでの階層を制度の対象とするのか議論が必要」「民間賃貸住宅と公営住宅との家賃差額は相当あり、これを誰が負担していくのか」「公営住宅も地方では空きが目立つと聞いている。地域別・建物別の空室状況を明らかにしてほしい」「住宅用確保配慮者に貸し出すため住宅にコストをかけることにオーナーは不安を抱くはず。ファイナンスも含め側面支援が必要」といった意見が挙がった。
次回会合は、6月21日。今夏をめどに中間とりまとめを行なう。