長期優良住宅認定第1号、長谷工「ブランシエラ浦和」をみる
2009年6月にスタートした「長期優良住宅」認定制度。「いいものを作って、きちんと手入れをして長く使う」という国のストック重視政策にもとづき、これから建設されるマンションや戸建住宅のあるべき姿、スタンダートとなるべき認定基準だ。ただ、マンションについては、要求される技術水準やコストの問題から、取り組んでいる企業はまだ少数。そうしたなか、同認定をトップでクリアしたのが、(株)長谷工コーポレーションの「ブランシエラ浦和」(さいたま市浦和区、総戸数69戸)だ。国の認定基準に加え、同社独自の技術や販売ノウハウがふんだんに盛り込まれた同マンションを紹介したい。

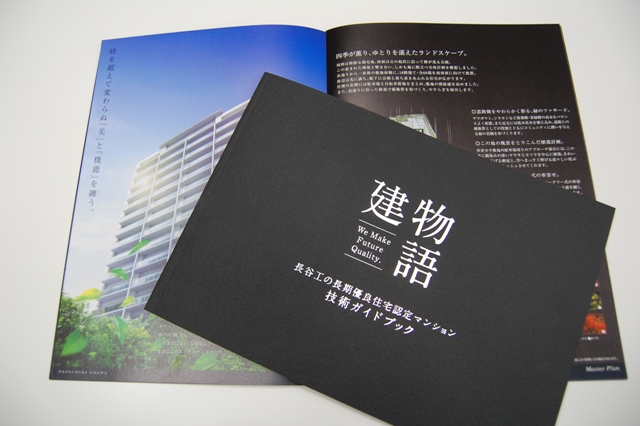








コストで二の足。まだ少ない「長期優良住宅」マンション
国が定める「長期優良住宅」とは、一言で言えば、これまでの住宅では考えられなかった耐久性と、それを維持するための維持管理・更新の容易性、居住者のライフスタイルに合わせるための可変性、優れた省エネルギー性、バリアフリー性能などが具備された住まいのこと。09年6月施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」により認定基準が定められ、09年末までに約3万8,000戸が「長期優良住宅」として認定されている。
しかし、マンションについては、09年末時点でわずか539戸と、認定をクリアした物件はほとんどない。なぜか。言うまでもなく、コストの問題だ。
実は、長期優良住宅に求められる技術は、ほとんどが特殊なものではない。どのディベロッパーに聞いても「やろうと思えばできますよ」という答えが返ってくる。だが、同住宅に対応することで、否応なく建設コストは膨らんでいく。
たとえば、住宅性能表示制度上の耐震等級「2」以上が求められるが、今販売されている多くのマンションは、建築基準法上問題ない耐震等級「1」。壁と柱をちょっと増やすだけで最高等級「3」が取得できる戸建住宅と違い、マンションが耐震等級を1つ上げるには、莫大なコストがかかる。
また、徐々に高まってきたとはいえ、マンションユーザーの「永住志向」はまだまだ低い。つまり、必要以上の耐久性や可変性を求めていないのも、事実である。
だが、そうしたユーザーも、長谷工コーポレーションが総力を挙げて世に問う「ブランシエラ浦和」を見れば、考え方が改まるはずだ。同社が「マンション革命」(常務執行役員都市開発部門・吉田隆一郎氏)というほど、そのインパクトと意義は大きい。
維持管理、可変性に独自の技術導入
「ブランシエラ浦和」は、JR東北本線「浦和」駅徒歩9分のスーパー跡地に建設される、地上18階建てのマンション。本来なら、ロケーション等についても述べたいところだが、今回は長期優良住宅としてのハードに絞って解説したい。なにしろ、モデルルームでも技術紹介「だけ」のコーナー(シアター・実大展示)があるし、通常のパンフレットとは別に、詳細な解説書を渡しているほど、同物件の「キモ」となるからだ。
建物は、長期優良住宅認定制度に定められる9つの基準をクリアしているほか、長期優良住宅の普及と技術革新を図ることを目的とした、国土交通省「長期優良住宅先導的技術提案」にも認められた同社独自の技術を導入している。代表的なものを紹介したい。
長期優良住宅は3世代(概ね90年以上大がかりな改修不要)という耐久年数の非常に長いコンクリートが使われる。だが、ガス・水道の配管やサッシュなどは、それほどの耐久性が望めず、一定期間での更新が必要となる。そこで、同マンションでは、設備配管を住戸内から住戸外へ変更。排水立て管は特殊継ぎ手を使って容易に交換できるようにした。また、同社独自の想定耐用年数200年というステンレス共用給水配管も導入している。
一方、住戸の外装(戸境壁を除いた開放部)には、「クラディングシステム」と呼ばれる技術を導入している。通常、玄関ドアやサッシュは、外壁に設けたレールに枠を溶接しそこに結接されるため、部材の交換が必要となった場合、大がかりな解体工事が必要となる。「クラディングシステム」は、サッシュユニットを溶接せず、すべてボルトで固定。さらにサッシュ枠はALCパネルで挟み込んだ。これにより、サッシュや玄関ドアの交換が容易にできるほか、構造体から分離・稼働するため、地震が起きても変形が最小限で済むという「おまけ」までつく。
住戸内は、スケルトン・インフィルの考えをベースに、躯体天井高2,700mm以上を確保、二重床・二重天井とし、同社独自の新内装システム「床先行工法」を採用した。通常の二重床は、躯体に間仕切り壁を固定したあと、部屋毎に二重床を施工する「壁先行」工法だが、これだと間取り変更で壁を移動する場合、床を一から貼り直す必要がある。床先行工法なら壁を撤去したあと仕上げ材を補修するだけで済む。
建物クオリティの向上とともに、アフターサービスも充実させた。これまで2~5年だった専有部へのアフターサービス期間を5~10年に、共用部は10年から15年へと延長。3ヵ月、1年目、2年目の専有部定期補修対応は、さらに3年目、5年目を追加。共用部についても20年目を迎えるまで、技術スタッフによる定期点検を行なうなど、大幅に強化・拡充した。
専有面積は80~131平方メートル。最低でも6,800mmスパンが確保されている。
「間取りが存在しない」マンション
ハード以上に特徴的なのが、その販売手法だ。
誤解を恐れない言い方をすれば、このマンションの住戸に「間取り」は存在しない。あるのは、専有面積が決まったスケルトンだけだ。もちろん、そこにフィットする「基本間取り」や、その間取りを標準の設備仕様で仕立てた場合の販売価格はちゃんとユーザーに示される。だがこのマンションでは、ユーザーがライフスタイルに合わせ、さまざまなスタイルと設備仕様の間取りを決めることができる。それを実現するのが、新たに導入された「E-Label(エラベル)」システムだ。
同システムは、同社がこれまで展開してきた間取りのメニュープランと、「U's style」(設備オプションセレクト)、「アイセルコ」(住宅ローンに組み込めるオプション仕様)、「Be-Liv」(オプション部位の大幅拡大)を発展統合。間取りから設備仕様まで、ニーズに限りなくマッチした住戸を実現するもの。
ユーザーはまず、8~12通りのメニュープランから間取りを選択し、25パターン(床5種類×建具5種類)の内装カラーと、キッチン、洗面化粧台、浴室の天板・パネルを選んでいく。次に、設備と建具類の仕様についてグレードアップメニューを決めていく。それらの組み合わせは、実に数万通りに及ぶという。
各住戸には、グレードアップのための「枠」として、50万~60万円分の「ポイント」が与えられており、この範囲であれば、負担はない。また、負担分については、住宅ローンへの組込みを可能としている。
SI仕様のため、(施工期間の制約はあるものの)間取りも水回りの移動も自由自在。たとえば、部屋数を減らせば、壁施工費が減る。それを設備仕様のグレードアップに回すなど、上限予算を決めたうえで理想に近づけていくといった芸当もできるのだ。
「モデルルームのように、自分で見つけてきた高級キッチンを置くこともできますし、『あと数年もしたらもっといいキッチンが出るはず』とあえて安いものにして、あとから望みのキッチンに入れ替えるといったことも可能です」と、販売を担当する(株)長谷工アーベスト受託販売第四部門兼受注営業部部門長・遊佐康人氏は、この販売手法に自信をみせる。
補助金の恩恵で価格上昇なし
さて、価格はどうか。
同社から公表された予定価格は、専有面積80平方メートル台の最多価格帯が、5,000万円台ということだけ。そこから想定できる坪単価は、230万円程度であり、浦和駅周辺の新築マンションとほぼ同水準だ。
長期優良住宅対応のスペックとしたことで、建築費は約15%上がっているそうだが、これらは国からの補助金で相殺できるため、「販売価格に転嫁することはない」(吉田氏)という。従来型マンションを上回るアフターサービス・維持管理システムが享受できること、住宅ローン、税制へのさまざまな恩恵など、ユーザーのメリットも計り知れない。
記者は、長期優良住宅は、自動車業界で言えば「ハイブリッドカー」や「電気自動車」のようなものだと考えている。これらはランニングコストや環境性能において飛びぬけた性能を持っているが、価格も高い。だが、さまざまな補助金や税制メリットをユーザーへ丹念に訴求し、補助金や自助努力で価格を抑えさえすれば、車の「プリウス」や「インサイト」のような爆発的ヒットもある。
同マンションも、モデルルームオープンから2週末で、すでに来場が130組を突破した。販売結果が楽しみだ。(J)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



