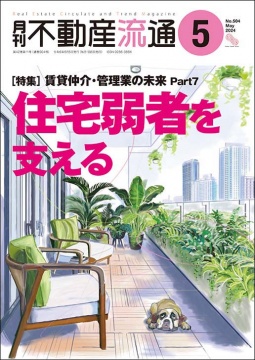(公財)日本賃貸住宅管理協会・家賃債務保証事業者協議会は19日、令和3年度第1回定例会をオンライン形式で開催した。
定例会では、国土交通省住宅局安心居住推進課安心居住係長の小越康史氏が、家賃債務保証業者登録制度の現況について報告した。同制度への登録事業者は、6月30日時点で81社。
同省が行なった管理会社への調査では、家賃債務保証業者を利用するケースは約8割(平成30年度調査:約6割)と、大きく伸長。賃借人を対象とした調査では、約4割が「現在、家賃債務保証業者を利用している」と回答した。しかし、同制度の認知度は「あまり知らない・まったく知らない」との回答が6割超を占めた。
また全国の消費生活センター等が受けた苦情・相談件数は、2010年度の727件をピークに、17年度以降は500件台で推移し、20年度は500件を下回った(497件)とした。
続いて、日管協総合研究所主任相談員の鈴木一男氏が家賃債務保証に関する相談業務について説明。同研究所に寄せられた相談件数は1,355件(令和2年4月~令和3年3月)のうち、家賃債務保証に関する相談は59件(全体の約4.4%)で、内訳は支払督促関連22件(37.3%)、契約内容関係6件(10.1%)、更新関連3件(5.1%)、その他28件(47.5%)。同氏は、「強引な支払督促行為は依然として現場で多く発生している。相談者が、保証委託契約の内容を十分に理解していないことによる相談も多い」とし、「保証委託契約締結の代理店である仲介会社や管理会社は、借り主への丁寧な契約内容の説明が求められる。保証会社としての方針やコンプライアンスの遵守が、現場まで徹底されることも必要」とコメントした。
ことぶき法律事務所弁護士の亀井英樹氏は、賃借人が死亡した場合の事務処理に関し、法律面から解説。国土交通省が公表した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」について、ポイントを挙げながら詳解した。「残置物処理契約は、高齢の単身者を賃借人とする賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の賃貸借契約の解除や、残置物の処理において極めて有効な手段となることは十分に予想できる」と言及。「同契約は、死後事務委任契約の一部に過ぎないため、さらに死後事務委任契約を追加して、事務の範囲を拡大していくことも今後は考えられる」と述べた。
(株)アミックス賃貸事業本部本部長の深澤成嘉氏は、「電子契約におけるメリットや留意点とは」をテーマに講演。「家賃保証会社の契約書の電子化により、数千万円以上のコスト削減が見込まれる」とメリットを述べ、「スマートフォンがあれば契約手続きは可能。多要素認証等で本人性や同意取得を担保できる」とした。また、5月に成立したデジタル改革関連法にも触れ、「同法には宅建業法の改正も含まれており、施行されれば完全オンライン契約が実現する。家賃債務保証事業者が先導して電子化を進めていくのはハードルが高い。パートナーである管理会社と連携し、電子契約化を進めていただきたい」などと話した。