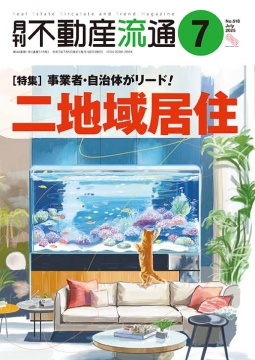国土交通省は26日、「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」(座長:鎌野邦樹早稲田大学法学学術院法務研究科教授)の3回目の会合を開催。「外部専門家の活用ガイドライン」改訂の方向性について議論した。
事務局が検討すべき論点(案)を提示。(1)第三者管理者方式を導入する場合のプロセス(既存マンション)、(2)同(新築マンション)、(3)管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)、(4)第三者管理者方式における、管理組合の財産の分別管理のあり方、(5)管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス、(6)利益相反取引等のプロセスと情報開示のあり方、(7)大規模修繕工事のプロセス、(8)監事の設置と監査のあり方、を挙げた。
改訂するガイドラインへの記載内容について、(1)では導入検討段階において、管理業者は理事会に対し、第三者管理者方式に関するメリットだけではなくデメリットを含め、「管理者の権限の範囲」「通帳・印鑑の保管方法」「管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス」などについて説明することが望ましいと提示。(2)については、「既存マンションの導入時との違い」「契約締結前までのプロセス」「契約締結時、その後のプロセス」を追記するとした。(3)では、管理者業務委託契約は管理業務委託契約の別紙として取り扱うのではなく、別々の契約書を交わすことが望ましい旨を追記した。(4)の分別管理については、管理組合財産の口座名義は「〇〇マンション 管理組合」など、管理組合の預金口座であることが一見して明らかとなるような名義とすることが望ましいとしている。
(5)の管理者の任期については、原則的に1年間とすることが望ましい旨を追記。(6)では、「災害等の緊急時においては、総会の決議によらず、敷地および共用部分等の必要な保存行為(当該取引が自己取引または利益相反取引に当たる場合を含む)を行なうことができる」という条文を設けることも考えられるとした。(7)の大規模修繕工事については、区分所有者および外部専門家たる監事から構成される修繕委員会を主体として検討することが望ましい旨を追記。(8)の追記内容として、「監事を設置するべき旨」「監事は総会の決議により選任するべき旨」「区分所有者は、監事の選任の際には、監事候補者が独立した立場から管理者に対して適切に監視する機能を果たせるかについて、十分に検討することが望ましい旨」とした。
これらについて、委員から「第三者管理者方式に関する“リスク”についても説明すべきでは」「できるだけ早い段階で消費者に多くの情報を開示することが望ましい」「管理業務の担当者にマンション管理士を含むべきではないのでは」「監査業務の事務負担が大きいことから、監事がどの程度の役割を担うのかについて十分に考えるべきでは」などの意見が挙がった。
次回は2024年1月26日に開催。「外部専門家の活用ガイドライン」の改正案について議論していく予定。