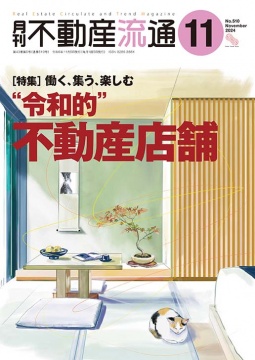国土交通省は24日、「今後の市街地整備の在り方に関する検討会」(座長:岸井隆幸日本大学理工学部土木工学科特任教授)の報告を公表した。市街地整備にどのように取り組むべきか、その方向性等が示されている。
価値観やライフスタイルの多様化により、市街地に対する評価軸が大きく変化。市街地が量的に充足してきたこともあり、今や市街地は、人にとって居心地が良いか、人との関係が生まれるかどうかといった、「アクティビティがもたらす価値」が重要と考えられるようになってきている。
その一方で、既成市街地では一定の整備が行なわれてきたものの、十分な基盤整備がなされていない既成市街地や防災性向上が求められる木造密集市街地も依然存在している現実がある。そのため堅牢性の高い建物、都市基盤等の老朽化や陳腐化、高まる災害リスクといった課題への対応は必須である。さらに、エリアを見渡したトータルな視点から課題を把握し、解決を図ることが重要であり、これまで進められてきた「『空間』・『機能』確保のための開発」から『『価値』・『持続性』を高める複合的更新」を進める「市街地整備2.0」と呼ぶべき考え方への転換が必要である、とした。
そのための方策として、市街地整備手法の在り方については、整備済みの道路等の都市基盤について必要に応じ土地区画整理事業等による再編等を進め、すでに高度利用がされているものの老朽化・陳腐化が進行した耐火建築物であるビル群について、市街地再開発事業のほかに、任意建替やリノベーション等の手法により、機能更新を図り、エリアとしての価値を維持・向上させるとともに、まちなかの市街地を再構築していく必要がある、と指摘。
そして「高度利用」の考え方については、必ずしも事業前に比較して物理的建物を増大させることを意味するものではなく、市街地再構築に当たっては、必要に応じて一定の強制力を持って着実に進めていくことが可能な法定事業を適切に活用することも有効である、とした。
また、持続可能性確保・競争力強化の観点から、立地適正化計画等との連携により再編を進めていくことが重要。その際、都市機能の器として都市基盤・建物の空間を確保するのではなく、都市機能の導入がさまざまなアクティビティの展開につながるような市街地へと再構築し、価値・持続性の向上につなげていく必要があると共に、その受け皿となる市街地についても、さまざまな空間利用のニーズへの対応が必要であるとしている。
その他、水災害リスクへの対応を含めて安全な都市形成を推進することが必要で、エリアの活性化や魅力増進を図るために、整備後の継続的な活用を視野に入れ、多様な地域活動と連携し、持続的に価値を生み出す地区経営の視点の必要性についても触れている。